結論から言えば、
夏休み明けに心が重いと感じたら、
まずは立ち止まり「逃げてもいい」。
逃げることは現実からの撤退ではなく、
命と心を守るための合理的な戦略であり、
次の一歩へつなぐための選択です。
9月の壁は「本当に」ある
毎年、長期休み明けは
子どもの自殺が増える傾向が確認され、
特に9月1日前後は統計的にも
突出する時期とされています。
この背景を前提に、
国や自治体は面談やアンケート、
見守り強化などの対策を通知しており、
「しんどい」は個人の弱さではなく
社会が一緒に扱うべきサインとして
位置づけられています。
「逃げる」は弱さではない
私は大人として、
逃げることを推奨します。
体と心が危険信号を出しているとき、
場所ややり方を変えることは、
自分を守るための正しい判断です。
学校に行かないという選択や、
時間差登校・別室・フリースクール・
家庭での学びなど、学びの形は
複数用意されています。
具体的な逃げ方の設計
- 時間をずらす:
遅れて行く、午前だけ行く、
保健室・別室で過ごすなど段階をつくる。 - 場所を変える:
地域のフリースクール、子ども食堂、
プレーパークなど
「学校以外の居場所」を利用する。 - 役割を減らす:
部活休止、委員会・生徒会の一時停止、
提出物の延長相談など負荷を下げる。 - デジタル相談を使う:
SNS相談やオンライン面談はハードルが
低く、早期発見・支援に役立ちます。
連絡の一言テンプレ
- 先生へ:「体調が不安定なため、
当面は別室・短時間登校で
調整させてください」 - 家族へ:「いまは安全第一で、
登校形態を見直したい。
相談先と一緒に考えたい」 - 友人へ:「少し距離を置くけど、
落ち着いたら連絡するね」も
立派な自己防衛です。
相談先リスト(保存推奨)
- 24時間子供SOSダイヤル:
全国どこからでもつながる教育委員会の
相談窓口。夜間・休日も対応。
- 学校・教育委員会:
長期休み前後の面談、相談、
見守り強化の体制あり。
配布物やポータルを確認。 - 地域と民間の居場所:フリースクール、
子ども食堂、キャンペーン企画の
受け皿などが開放されています。 - ネット・スマホ相談(東京都):
オンラインの具体的アドバイス窓口も
活用可能です(各自治体版も確認)。
大人の責任としての「合図の受け取り」
私は「行きたくない」を、
怠けではなくSOSの合図として受け取ります。
声をかける時は「みんな行ってる」「甘え」
は避け、体調と安全を最優先に、
段階的に支援計画を作るのが基本です。
学校側も“1人1台端末”の健康観察や面談など、
早期把握に舵を切っています。
最新動向から見える選択肢
- 夏休み明けの不登校支援は各地で
イベント・研修・相談体制が整備され、
先生側の学び直しも進んでいます。 - 発達特性のある子どもの不登校は
平均より高く、画一的な登校再開だけ
ではなく、多様な選択が必要です。 - 政策面でも「学びの多様化」「特例校」
「別室支援」の拡充が提案・実装され、
逃げ道ではなく“別ルート”として認知が
進んでいます。
最後に
逃げることは、
生き延びるための科学的で社会的に
認められた「作戦変更」です。
今日の一歩は、小さくていい——
時間をずらす、場所を変える、
誰かに連絡する、そのどれもが
次の明日を連れてきます。
ここまで読んだなら、
今すぐ一つだけ行動を選んでください。
「電話」「メッセージ」「休む」の
それだけで十分です。

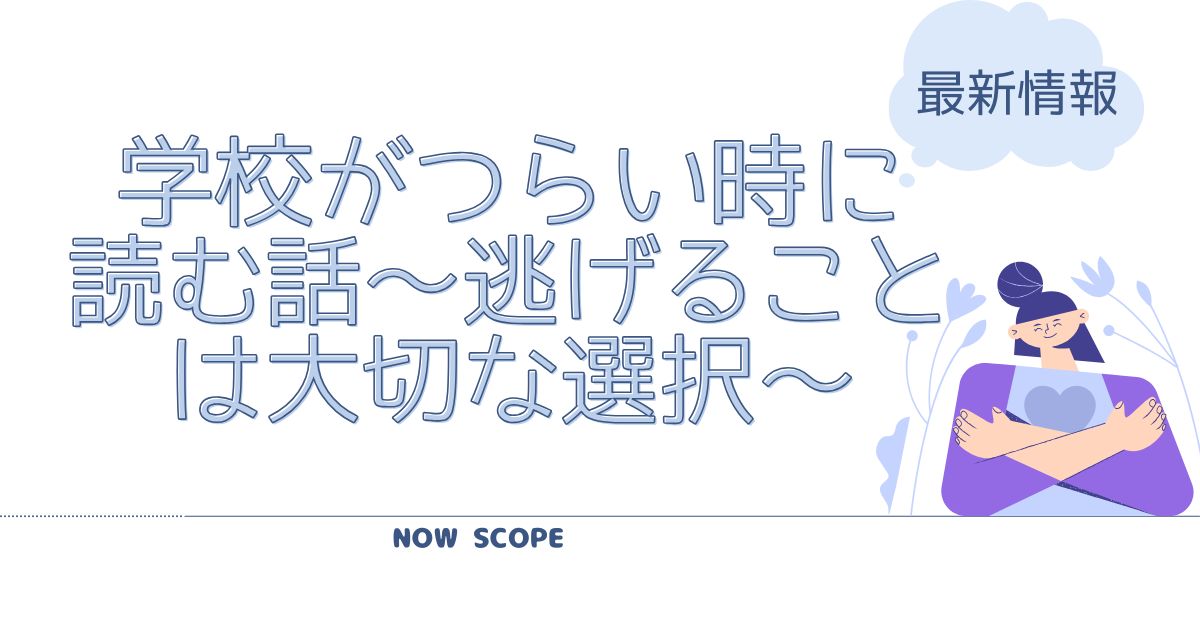
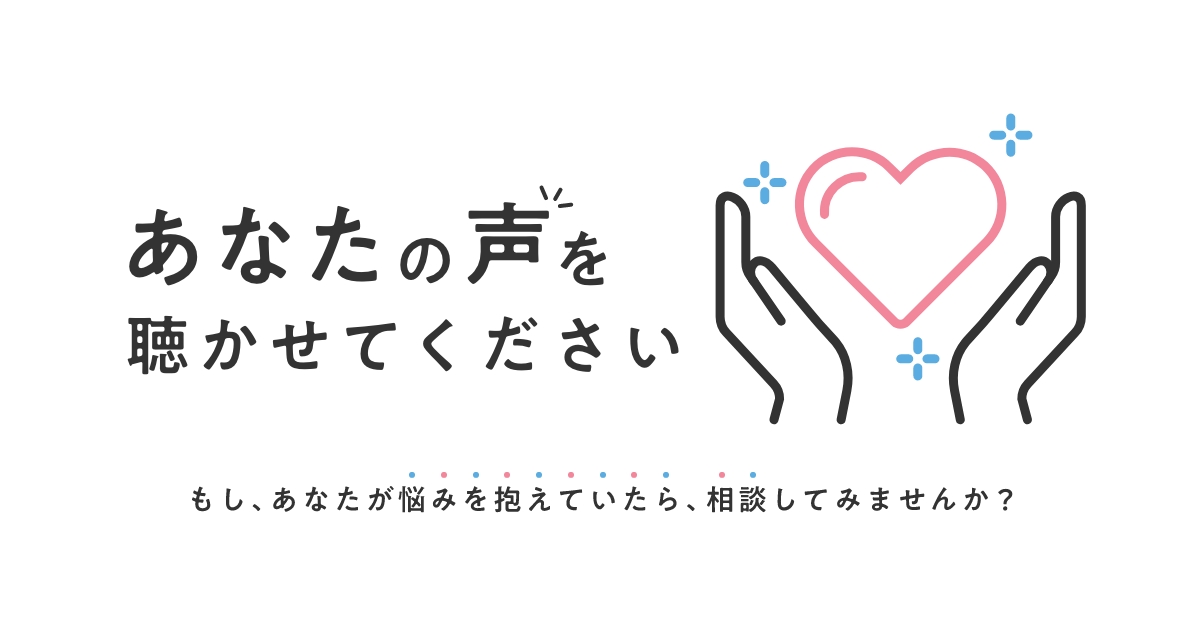


コメント